インプラント治療は、失った歯の見た目や噛む機能を回復できる高精度な歯科治療の一つですが、その費用は決して安くはありません。1本あたり数十万円かかることも多く、費用面から治療をためらう方も少なくないでしょう。
こうした負担を軽減するために活用できるのが「医療費控除」制度です。条件を満たしたうえで申請すれば、支払った費用の一部が後から還付される可能性もあります。
この記事では、医療費控除の仕組みや対象条件、インプラント治療で控除できる費用・できない費用、計算方法までわかりやすく解説します。インプラント治療をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分を課税所得から差し引き、所得税や住民税の負担を軽くできる制度です。
対象期間は1月1日〜12月31日までの1年間で、合計10万円または総所得金額の5%のいずれか低いほうを基準として、それを超えた分が控除されます。さらに、本人だけでなく扶養している配偶者や子ども、親などの医療費も合算可能です。
たとえば、自分の治療費8万円と子どもの治療費5万円を合わせて13万円になれば、基準額を超えるため控除の対象となります。
この制度を活用して確定申告すると、税金の負担が軽くなったり、納め過ぎていた税金が還付されたりする可能性があります。
インプラント治療は医療費控除の対象になる
インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります。国税庁が公表している「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」にも、インプラント手術や関連する処置が明記されています。
また、混同されやすいのが「控除」と「還付」の違いです。
- 控除:支払った医療費分を課税所得から差し引くこと
- 還付:控除の結果、払い過ぎていた税金が戻ること
医療費控除は「税金を直接返してもらう制度」ではなく「課税対象の金額を減らして税額を計算したうえで、税金が戻ることもある」のが特徴です。
還付額は所得や医療費の合計によって変わるため、気になる方は「インプラントの医療費控除でどのくらい戻ってくる?計算方法と金額の目安」を参考にしてみてください。
インプラント治療は高額療養費制度の対象外になる

医療費の自己負担を減らす制度として、高額療養費制度があります。
高額療養費制度とは、公的医療保険が適用される治療に対し、自己負担額の上限を超えた分が払い戻される仕組みです。虫歯や歯周病治療など、一般的な保険診療には利用できますが、自由診療であるインプラント治療は対象ではありません。
インプラント治療は、数十万円単位の費用を全額自己負担するケースも多く、経済的な負担を感じやすい治療でもあります。そのため、費用面の負担を軽減するには、医療費控除の活用が現実的な方法といえるでしょう。
医療費控除は保険診療かどうかを問わず、対象条件を満たせば申請できるため、インプラント治療を検討する際には確認しておきたい制度です。
インプラント治療で医療費控除の対象になる費用
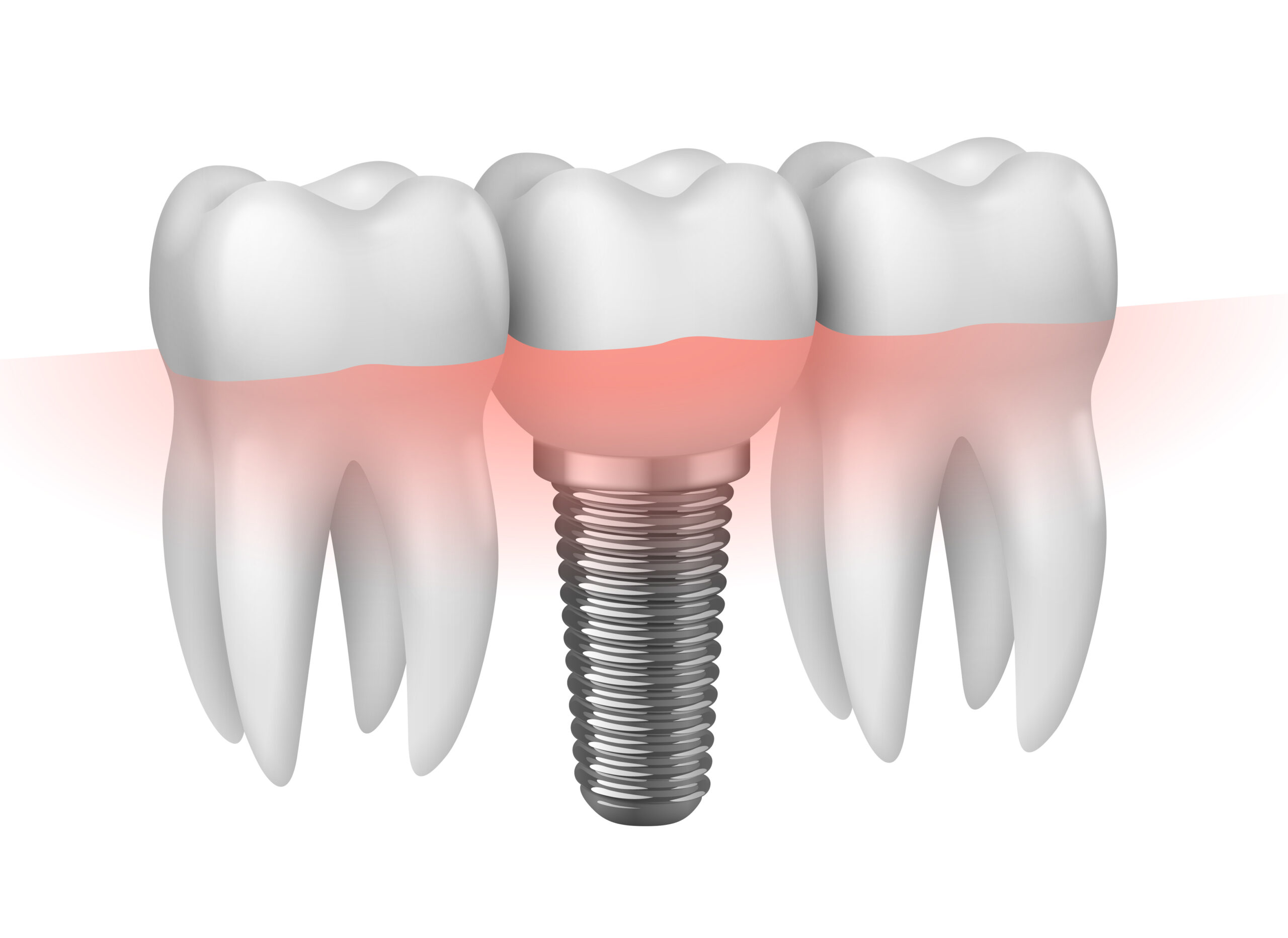
インプラント治療でかかる費用の多くは、医療費控除の対象になります。
対象となる費用は、以下の通りです。
- 手術費
- インプラント本体・人工歯の材料費
- 手術前後の検査費
- 通院時にかかった交通費・宿泊費
さらに上記以外にも、骨造成や麻酔といった治療に付随する処置費用も対象に含まれます。治療に直接関わる支出であれば、対象になるケースがほとんどです。
ここからは、医療費控除の対象となる代表的な以下の費用について、具体的に解説します。
- 本人または扶養家族のために支払った医療費
- 治療目的の交通費や宿泊費
- 分割払いやローン、クレジットカード決済でも条件を満たせば対象
本人または扶養家族のために支払った医療費
医療費控除は、申請者本人だけでなく同一生計の家族の分も合算可能です。
配偶者や子ども、親などが対象ですが、別居している家族でも生活費を送っている場合などは対象になるケースもあります。
たとえば、本人の治療費が8万円、扶養している子どもの治療費が6万円の場合。合計14万円となり基準額(10万円または所得の5%)を超えるため控除対象です。
家族全員の領収書をまとめて申告することで、控除額を増やせる可能性があります。
複数人分の領収書をまとめるときは、誰の治療費かが分かるように整理しておくこと、申告や確認時スムーズに進められるでしょう。
治療目的の交通費や宿泊費
インプラント治療の通院にかかった公共交通機関の運賃や、必要な宿泊費も控除対象です。遠方の専門医院に通う場合や、複数回の手術で宿泊が必要な場合も含まれます。
ただし、治療以外の目的で発生した費用や、過剰な宿泊費は対象外となるので、注意が必要です。
たとえば、治療と観光を兼ねた長期滞在や、高級ホテルの利用料金などは控除対象として認められません。
治療目的の交通費や宿泊費は、領収書やICカード履歴を保管し、通院日と一致することを証明できるよう診察券や予約票と一緒に整理しておくと安心です。
分割払いやローン、クレジットカード決済も条件を満たせば対象
支払い方法が分割払いやデンタルローン、クレジットカードであっても、実際に支払った年の金額として控除対象になります。
たとえば、12月にデンタルローンを契約し、初回の引き落としが翌年1月の場合は、翌年の申告対象です。
また、ローンやクレジットに含まれる金利や手数料は、控除対象外なので注意しましょう。
歯科医院の領収書だけでなく、ローンの契約書やクレジットの明細書もあわせて保管しておくとスムーズです。
インプラント治療で医療費控除の対象外になる費用

インプラント治療にかかった費用のすべてが、医療費控除の対象になるわけではありません。
特に「治療に関係するから大丈夫だろう」と思い込みやすい交通費や、美容関連費用には注意が必要です。
以降では、医療費控除の対象外となる代表的な費用を紹介します。
- 他人からの補填や保険適用分の費用
- 美容目的や審美治療の費用
- 自家用車での通院によるガソリン代や駐車場代・タクシー代
- 治療以外の通院にかかる交通費や宿泊費
他人からの補填や保険適用分の費用
インプラント治療でかかった費用のうち、保険会社や勤務先から給付された医療費補助や給付金など、第三者から補填された金額は医療費控除の対象外です。
控除できるのは、あくまでも自己負担分のみという点に注意しましょう。
また、インプラント手術の前後で保険診療(抜歯や歯周病治療など)を併用した場合、保険適用分は控除対象に含められません。控除できるのは、あくまでも自由診療として支払った部分のみです。
補填や保険適用の有無が分かりにくいときは、領収書や保険明細を確認し、必要に応じて歯科医院や保険会社に問い合わせると安心です。
美容目的や審美治療の費用
医療費控除の対象は、噛む機能や健康の回復を目的とした治療費に限られます。美容目的での治療や、審美処置は対象外です。
たとえば、インプラント上部の人工歯をより美しくするためのオプション費用や、セラミックの色合わせを目的とした追加費用については、控除になりません。
機能回復と審美目的の治療が混在している場合は、どの部分が対象外になるかを事前に歯科医院に確認し、領収書に明記しておいてもらうとよいでしょう。
自家用車での通院によるガソリン代や駐車場代・タクシー代
インプラント治療の通院にかかる自家用車のガソリン代や駐車場代、タクシー代は原則対象外です。医療費控除で認められるのは、電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の交通費のみです。
ただし、公共交通機関が利用できない特別な事情がある場合(緊急時や身体的理由によるものなど)は、例外的に認められることもあります。その際は、医師の指示や診断書、状況を説明できる書類も準備してから申告すると安心です。
治療以外の通院にかかる交通費や宿泊費
治療そのものと直接関係のない交通費や宿泊費は控除対象外です。
たとえば、治療後に観光を兼ねて宿泊した費用や、付き添いの者が観光目的で利用した交通費は当然申請できません。
申告する際は、領収書と治療日が一致しているか、治療目的であることを証明できるかを確認するのがポイントです。診察券や予約票を一緒に保管しておくと、税務署から問い合わせがあってもスムーズに対応できます。
インプラントの医療費控除でどのくらい戻ってくる?計算方法と金額の目安

医療費控除を利用すると、どのくらい税金が減るのか、実際にいくら還付されるのか気になる方も多いでしょう。
ここでは、控除額や還付金の計算方法について解説します。
- 医療費控除対象額の計算方法
- 還付金の計算方法
- 住民税の計算方法
医療費控除対象額の計算方法
医療費控除の対象額は、以下の式で求められます。
■年間所得が200万円以上のケース
医療費控除対象額=1年間で支払った医療費合計−補填額(保険金など)−10万円
■年間所得が200万円未満のケース
医療費控除対象額=1年間で支払った医療費合計−補填額(保険金など)−所得の5%
補填額とは、保険の給付金など、医療費の一部を第三者が負担した金額を指します。
また、この式で引かれる「10万円または所得の5%」は、自己負担として想定されている基準額で、その額を超えた分が控除対象となります。
どちらが低い方を基準としますが、目安として、年収200万円以上であれば「10万円」が基準額となり、200万円未満の場合は「総所得金額の5%」になります。
還付金の計算方法
医療費控除で戻ってくるお金(還付金)は、控除額に所得税率をかけて算出します。
医療費控除は「課税所得を減らす制度」なので、課税額が軽減されることで、結果として税金が還付される仕組みです。
計算方法は、下記の通りです。
還付金=医療費控除対象額×所得税率
なお、所得税率は課税所得によって5〜45%と段階的に変わるため、人によって還付額は異なります。所得ごとの税率は、国税庁のホームページにも掲載されているため、気になる方は、確認しておきましょう。
参考:国税庁「所得税の税率」
住民税の計算方法
医療費控除は住民税の軽減にもつながります。住民税は前年の課税所得をもとに計算されるため、控除によって課税所得が減ると、その分住民税も下がります。
計算式は、以下のとおりです。
住民税額=(課税所得ー医療費控除対象額)×住民税率
住民税率は、多くの自治体で約10%前後となっているため、上記の式を使うと減税の目安を把握できるでしょう。
インプラントの医療費控除の申請方法と必要書類

インプラント治療で医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。
ここでは、申請に必要な書類や手続きの流れ、提出期限について詳しく解説します。
- 申請に必要な書類
- 申請の流れと提出先
- 提出期限
申請に必要な書類
医療費控除の申請には、主に次の書類が必要となります。
- 領収書
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書
- 本人確認書類
医療費控除を申請する際に領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があるため破棄しないように注意しましょう。
申請に必要な領収書は、インプラント本体や手術費、麻酔費、検査費、公共交通機関の交通費などが対象となり、ICカード履歴や切符の記録も証明として有効です。
申請時は、領収書の内容をまとめた医療費控除の明細書を作成し、国税庁のフォーマットを利用して記入します。実際に提出するのは、明細書と医療費控除を反映させた確定申告書、本人確認書類です。
申請の流れと提出先
医療費控除の申請は、以下の手順で進めます。
- 1年間の医療費を集計し、領収書をもとに明細書を作成する
- 国税庁の「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成する
- 書面であれば印刷して税務署へ持参または郵送、オンラインならe-Taxで送信する
- 還付金がある場合は、申請から1〜2か月後に指定口座へ振り込まれる
確定申告の申請は、e-Taxを利用すれば、税務署に足を運ばず自宅で手続きできるのが大きなメリットです。さらに、計算ミスを自動でチェックする機能や、還付までの期間が比較的短いのも魅力です。
ただし、利用にはマイナンバーカードとマイナポータルアプリ、読み取りに対応したスマートフォンを用意しなければなりません。e-Taxでの申請を検討している方は、事前にアプリのインストールやマイナンバーカードを準備しておくと安心です。
提出期限
確定申告の提出期限は、毎年2月16日〜3月15日です。この期間内に申告すれば、所得税の還付が受けられ、翌年度の住民税も減額されます。
また、還付申告は5年間遡って提出することが可能です。たとえば、2026年に申請する場合、2021年分まで遡れます。
e-Taxを利用する場合は、メンテナンスで使えない期間などもあるため、期限ぎりぎりではなく余裕を持って申請しておくとよいでしょう。
インプラント治療の医療費控除に関するよくある質問
ここでは、インプラント治療の医療費控除について多く寄せられる以下の質問について、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
- 年末調整で申請できますか?
- クレジットカードやローンで支払った場合でも控除対象になりますか?
- 家族の医療費を合算して申請してもよいですか?
- インプラント治療で医療費控除を申請し忘れた分は遡って申請できますか?
年末調整で申請できますか?
医療費控除は年末調整では申請できず、必ず確定申告で手続きする必要があります。
勤務先が行う年末調整は、給与所得に関する税額調整のみを目的としており、個人の医療費や交通費、扶養家族分の情報までは把握できない仕組みです。
年末調整と確定申告は、以下のように役割が分かれています。
- 給与所得に関する調整=年末調整
- 医療費や寄附金など個人事情に応じた申告=確定申告
インプラント治療は個人的な医療費に応じた申告にあたるため、控除したい場合は、必ずご自身で税務署に申告する必要があります。
クレジットカードやローンで支払った場合でも控除対象になりますか?
治療費の支払い方法に関係なく、実際に支出があれば控除対象になります。
クレジットカード払いの場合は、利用日ではなく決済日が属する年で判断される点に注意が必要です。
たとえば、2025年12月に利用し、2026年1月に利用分の支払いがあった場合は、2026年度の確定申告となります。
デンタルローンなどによる支払いの場合も、契約時ではなく実際に返済した年の金額ごとに申告します。
ただし、金利や手数料は医療費控除の対象外です。ローンを利用する際は、歯科医院の領収書だけでなく、ローン契約書や支払明細も保管し、医療費と手数料を区別しておくとわかりやすいでしょう。
家族の医療費を合算して申請してもよいですか?
配偶者や子ども、親など、同一生計の家族であれば、医療費を合算して申請できます。
ただし、別居していても生活費などを送っている場合は、同一生計とみなされ申請が可能なケースもあります。
たとえば、自分の治療費8万円と子どもの治療費5万円を合算して13万円となれば、基準額を超えるため医療費控除の対象です。
合算する際は、誰の医療費かがわかるよう領収書を整理し個別金額を理解しておくと、税務署から質問があった場合も、スムーズに対応できるでしょう。
インプラント治療で医療費控除を申請し忘れた分は遡って申請できますか?
医療費控除の申請を忘れていても、過去5年分までであれば遡って申請できます。
たとえば、2026年に申請する場合、2021年分までの治療費が対象になります。申請を忘れていた年の医療費が10万円、もしくは所得の5%を超えている場合は、還付申請することで払い過ぎた税金が戻る可能性があります。
ただし、遡って申告する際も、領収書や診療明細書などは必要です。これらを紛失している場合は、歯科医院に再発行を依頼できるケースもあるため、問い合わせてみてください。
過去分の申請も通常の確定申告と同様に、税務署窓口またはe-Taxで手続きできます。
インプラント治療なら永田歯科医院

東京都立川市の永田歯科医院は、日本補綴歯科学会の専門医・指導医を含む複数の高度資格を持つ歯科医師が在籍する歯科医院です。
各分野のプロフェッショナルが連携する「チーム医療」により、患者一人ひとりの症例に合わせた高精度な治療に取り組んでいます。
院内にはCTやマイクロスコープ、専用オペ室など大学病院レベルの精密設備を導入。骨や神経の位置を三次元で把握し、より安全で負担の少ない手術を実現しています。
また、恐怖心が強い方には、静脈内鎮静法(セデーション)により「眠っている間に終わる治療」も選択できるため、安心して受診できます。
さらに、初診カウンセリングやCT撮影が無料なので、治療前に不安や疑問を解消しやすいのも特徴です。治療費が高額になりやすいインプラントに合わせ、医療費控除対象の領収書や明細の発行、デンタルローンや分割払いの相談などにも対応しています。費用面と治療面の両方から、長期的に安心できるサポート体制を整えています。
インプラント治療をお考えの方は、ぜひ当院へご相談ください。
\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/
まとめ:インプラント治療を受けるなら医療費控除について正しい理解を

インプラント治療は、見た目や噛む機能を取り戻せる一方で、費用負担が大きい治療でもあります。
医療費控除を申告することで、確定申告の手間はあるものの、課税所得軽減や還付金など、経済的な負担を軽減できる可能性があります。
控除の対象範囲や計算方法、申請の流れを正しく理解し、治療費の計画を立てて安心して治療を進めていきましょう。

- 手術自体の痛みが不安で、踏み切ることができない
- 治療がうまくいくかどうか、長期的に問題なく使えるかが不安
- どの医師に治療を任せるべきか選ぶのが難しい
そんなあなたには、オールオン4の治療を専門に行う、東京都立川市柏町にある「永田歯科医院」がおすすめです!
- オペ中の痛みや恐怖心等を感じない「睡眠無痛治療」を実施しています。
- インプラントには10年間の保証が付いておりますので、ご安心ください。
- 埋入実績5,000本以上の経験豊富な医師が治療します。
まずはお気軽にご相談ください。
\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/






